ジェンダー研究
ジェンダー研究は、男性を人間の「標準」とする学問に異議を申し立てた女性学から出発した学問です。男性が「標準」とされるということは、社会のなかに存在する性差が不可視化され、またジェンダーを生み出す社会構造やイデオロギー、思想、歴史的文脈が問われてこなかったことを意味します。これを問題にするのがジェンダー研究であり、その対象は、すべての学問分野に及ぶといっても過言ではありません。逆にいうと、その対象の広さゆえに、多くのジェンダー研究者は、社会学、歴史学、文学、政治学、哲学など、従来の学問的ディシプリンのなかで活動しており、日本では「ジェンダー研究」を専門として打ち出している研究者はまだまだ少ないのが現状です。一方で、ジェンダーという鍵概念の
登場とともに、従来の学問の分類とは異なる形でのネットワーキングや知の産出方法が求められてきました。これに伴い、1990年代以降、ジェンダー視点をもつ研究者を領域横断的に集めた研究拠点を有する大学も次第に増えてきました。学問分野は不動のものではなく、解決すべき課題の変容とともにつくりかえられてきたのです。一橋大学社会学研究科が「ジェンダー研究」を一つの領域として掲げていることは、そのような知のフロンティアをつくりあげていこうとする姿勢のあらわれに他なりません。
ジェンダー社会科学研究センター (CGraSS)に集う教員たちの専門もまた、あらゆる学問分野にまたがっていますが(http://gender.soc.hit-u.ac.jp/)、地球社会研究専攻で「ジェンダー研究」を担当している教員3名は、社会学と歴史学(ジェンダー史)の方法を用いた研究を行っています。ジェンダー研究は女性学から出発し、これを受けて男性の立場からの省察をはじめた男性学、異性愛中心主義への批判と対抗のために登場したセクシュアリティ研究、さらに男/女や異性愛/同性愛といった二項対立そのものを脱構築しようと発展したクィア研究等を緩やかに包摂しつつ、時に緊張関係を孕みながら発展してきました。多様な方法論のもとに蓄積されてきた研究の成果を吸収しつつ、自分がどのような方法によって学位論文を執筆するのかを意識して学修をすすめていってもらいたいと思います。

佐藤文香 教授
- 研究領域
ジェンダー研究、軍事・戦争とジェンダーの社会学
大学院で「軍隊と女性」を研究テーマに選び、長らく自衛隊をフィールドとした研究を続けてきました。その過程で、英語圏におけるフェミニスト国際関係論という分野や日本国内の戦争社会学という新興分野に集う研究者と交流をし、戦争・軍事のジェンダー研究という分野の開拓につとめてきました。 これらの成果は、2022年の単著『女性兵士という難問』(慶應大学出版会)や2021-22年の編著『シリーズ 戦争と社会』(岩波書店)にまとめましたが、あと一冊、この関連で成し遂げたい仕事が残っています。現在、出版に向けた共同企画もいくつか進行していますが、ここ数年、特に力をいれているのが、第二波フェミニズムの理論的総括に関連した仕事です。単線的な進歩史観や善悪二元論に基づいた他者化とは異なる形でのフェミニズムの歴史叙述を模索し、ジェンダー理論の「失われた20年」を打開する方途を探っています。
進行中の研究プロジェクト
日本における第二波フェミニズムの成果と課題―理論的・実証的総括のために
【科研費 基盤研究C】
錯綜するフェミニズムの現状を整理し、「第二波フェミニズム」の思想的意義と達成、そして限界を考察しようとするものである。「第二波フェミニズム」を、改めて日本の歴史的文脈のなかに位置付けて理解し、その成果と課題を理論的・実証的に明らかにしたうえで、フェミニズムの新たな歴史叙述を模索していく。世代間の差異を強調した単線的な進歩史観を問い直し、日本のフェミニズムの評価を再検討することを目指す。
研究成果
戦争・軍事のジェンダー研究という分野の開拓につとめてきました。 これらの成果は、2022年の単著『女性兵士という難問』(慶應大学出版会)や2021-22年の編著『シリーズ 戦争と社会』(岩波書店)にまとめました
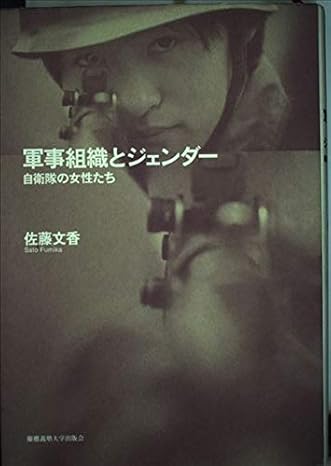
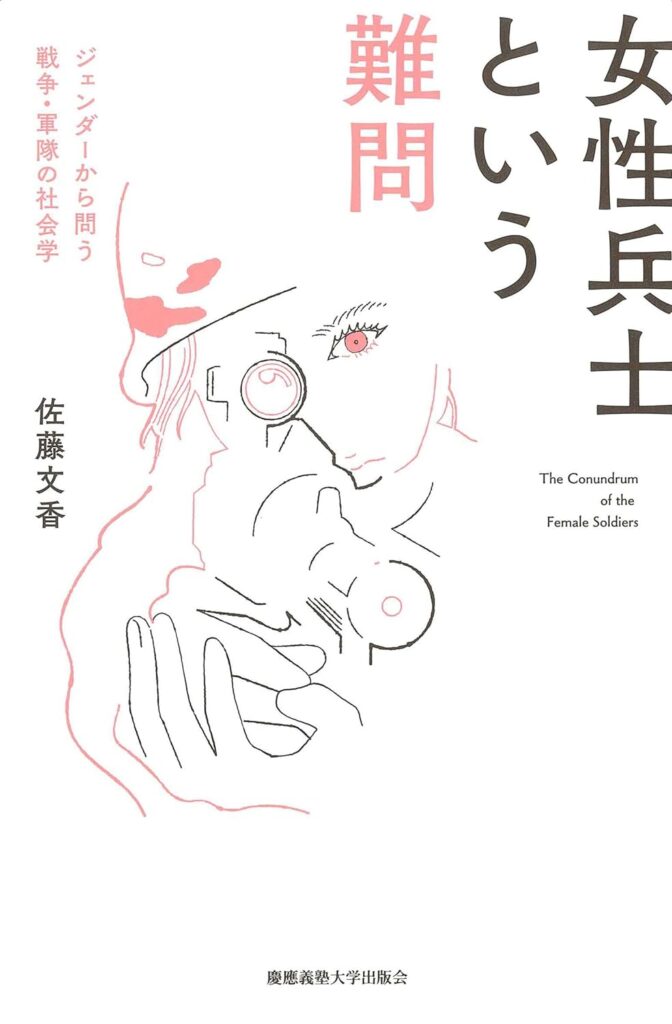

進行中の研究プロジェクト
近代日本における「性別」の成立と性差観の変容
【科研費 若手研究】
「ジェンダー」という言葉は、性差に対する私たちの認識を確実に変化させた。では、明治期に「性別」という言葉が新たにつくられたとき、それは人々の認識をいかに変化させたのだろうか。本研究は近世後期から近代にかけての男女差に関する言説を辿るなかで、明治期につくられた「性別」という観念が、いかに、どのようなものとして構築されていったのかを明らかにするものである。具体的には、男女差に関する医学的・科学的言説や民衆思想・民衆宗教における言説の分析を通して、生まれつきの男女差に対する理解の変容を明らかにするとともに、そうした変容が性表現や性役割の理解の仕方に与えた影響を検討する。

田中亜以子 専任講師
- 研究領域
ジェンダー史研究
ジェンダー・セクシュアリティをテーマとした歴史的研究を行っています。ジェンダーやセクシュアリティを歴史的考察の対象とするということは、私たちの社会に存在する性差や性役割、性別観、あるいは、性道徳や性行動等を自明のものとすることなく、その形成過程や、現代とは異なる時代の論理を考察することを意味します。
私自身は、これまで主に近現代日本における恋愛観・性愛観の形成過程を研究対象としてきました。恋愛や性愛は、ときに「本能」と結びつけられることもあり、人間の普遍的な行動として理解される傾向があります。しかし、たとえば、どのような恋愛や性愛を「正しい」ものとするのかということは、時代や文化によって大きく異なっています。具体的には、明治から昭和初期における恋愛観の形成、夫婦間セックスをめぐる規範の形成、ウーマン・リブ運動における「性解放」の主張、売春防止法の制定過程等を考察対象としてきました。


学部ゼミ生との出版プロジェクト
ジェンダー研究のゼミに所属していることで友人・知人から投げかけられた質問に回答するQ&A集『ジェンダーについて大学生が真剣に考えてみた』を出版
3.jpg)